国公立医学部合格へ⑭ 最短 物理 勉強ルート
物理は
最終的に何を目指すのか?
によって、どんな風に勉強するべきか?
がかなり異なる科目だったりします
工学部などで将来物理を絶対に必要とするなら、基本からしっかりやり込んで、妥協せず考え抜いて物理そのものを勉強していく必要もありますが...
地方国公立医学部に合格するための物理選択ということもありますので、ここではそういう人に向けてのアンサーとして書いてみようと思います
(賛否両論はあるとは思いますが...
他の教科も高得点を取る必要がある地方国公立医学部志望の人ので、あえて「学問追求ではなく、短期間で地方国公立医学部の入試で高得点が取れる流れ」を組み立ててみます)
参考書などを挙げていきますが
物理の参考書問題集は使い手を選びますので、「理解がしやすく得点に結びつけやすいと実感できるものを試していきながら選ぶ』ための選択肢として提示させていただきます
(どうしても物理が自分に合わないものであると思えるなら、無理をせず、生物選択を視野に入れておいてください)
講義物と問題集を併せて1冊〜3冊で済ませたいので、シリーズとして多い(こなすのが結局重くなる)ものは選ばない方針にしておきます
(冊数が増えれば増えるほど、結局はきちんとこなさなくなるものです)
そういう意味で
①〜⑤を1つ選んでみてください
参考書問題集で勉強をやり込んだら、『地方国公立二次試験過去問』をピックアップしてどんどんアウトプット演習をして、合格ラインを取ることへの流れを固めてください
→テンポよく確実に合格ラインを取る練習は、物理・化学においてはテスト演習に勝るものはありません
(理科では、テスト演習に早く移りたいがための、参考書問題集演習だということをよく意識しておいてください)
↓↓↓物理が苦手ならコレ↓↓↓
①『橋元の理系物理ⅠB・Ⅱ/橋元の理系物理Ⅰ・Ⅱ』(オススメ度★★★★☆)
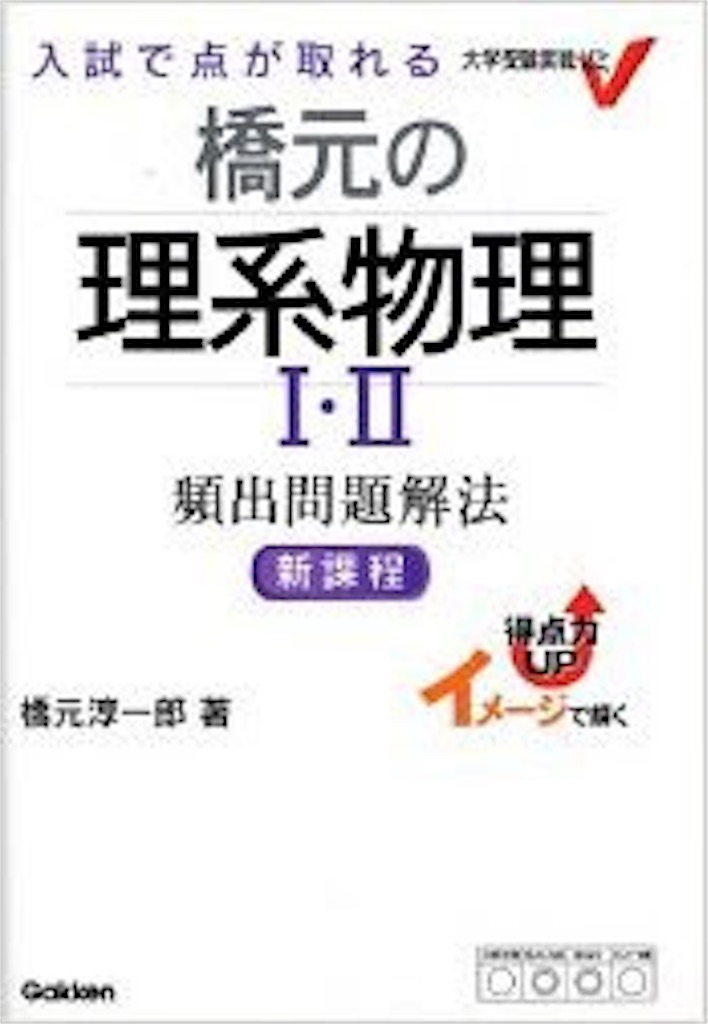
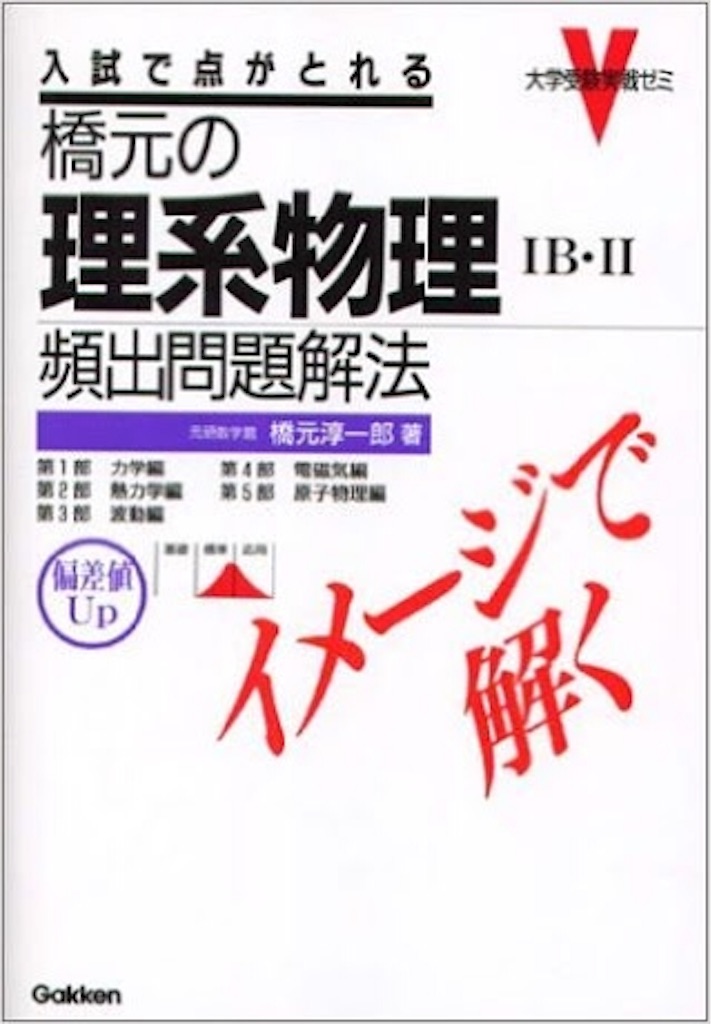
講義物(読み物)として、『橋元の解法の大原則1、2の2冊』をご用意していただくのも問題ないです
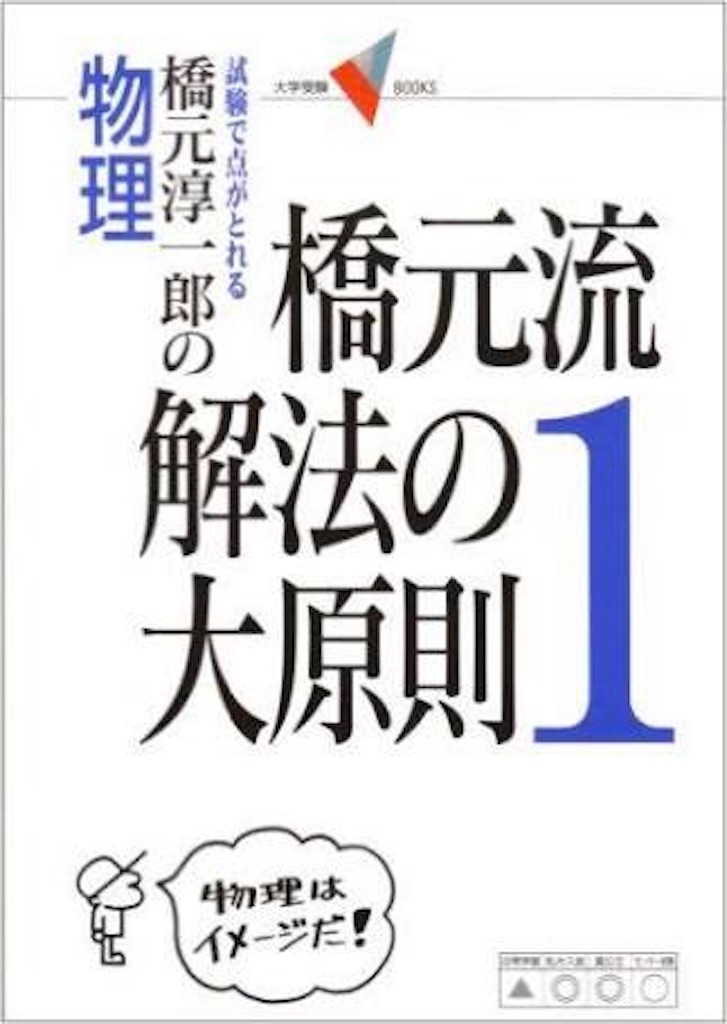
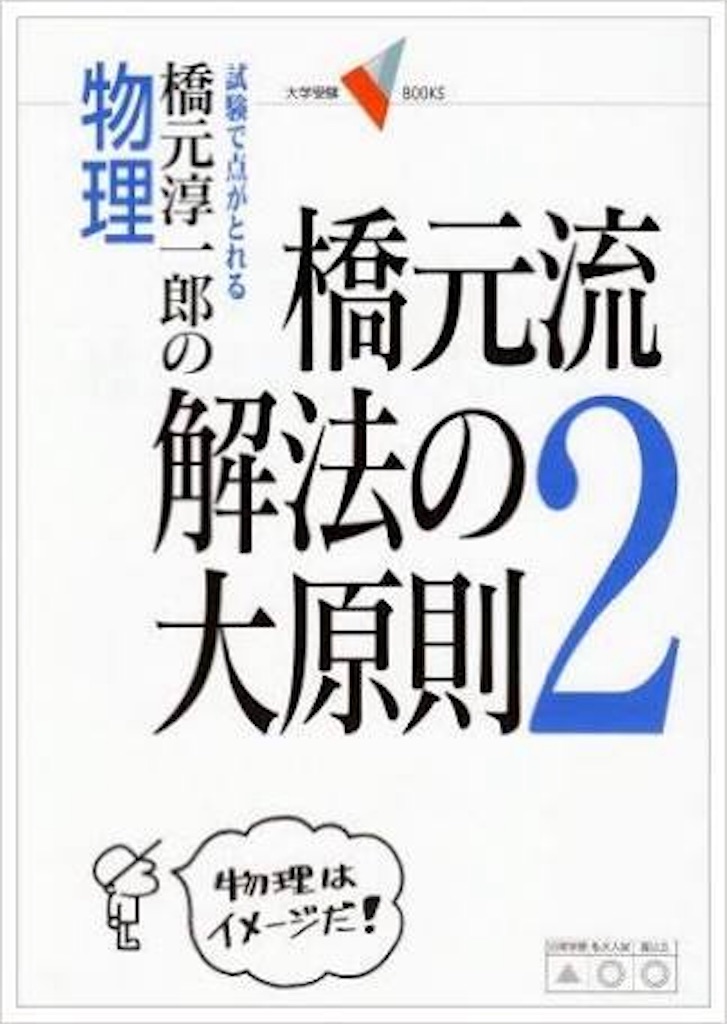
(今現在、新課程版としてのパワーアップ版は力学電磁気の1冊しかないので、手に入りやすい旧版をオススメします)
(↑オススメしてるものは全て廃版にはなっていますのでAmazonやメルカリやブックオフを探してみてください)
理系物理の別冊の冊子で物理の解法イメージをコンパクトにまとめながら(←かなり使える内容です)、少ない例題に対してかなり詳しい解説を施していき、類題にも解法のコツを図解している点が、物理苦手な人にも理解しやすく使いこなしやすい構成となっています
たしかに
イメージで物理を押し切る考え方は複雑な設定となった場合、行き詰まる傾向にはありますが、
(物理が難しくない)地方国公立医学部合格レベルに対しては、それほど困ることはないと思います
(実際、過去問をやり込む時に、自分で微調整をしていけば特に問題ない気もします)
↓↓↓物理が苦手ならコレ↓↓↓
②『秘伝の物理』(オススメ度★★★★☆)
講義物2冊...全てにYouTubeの講義つき
問題集...旧版(白く太い冊子)と同じ内容となっています
講義物で1つ1つ押さえながら、その単元に合う問題を解いて理解を深めていくといいとは思います
講義物の解説はシンプルに整理されていますが、YouTubeの動画と併せて観ていただくと言葉が足され、ちょうど良い理解が得やすくなっています
問題集は、補足説明も詳しく都度入れられて、理解がしにくいということはない丁寧な作りとなっていますので、オーソドックスな例題選定と相まって多くの人に使いやすいものとなっていますね
(問題集の方にも所々の分岐点となる問題にはYouTubeの動画で解説があります)
物理の「考え方」が身につきやすい内容となっていますが、その分、橋元先生よりは理解できる人のレベルを多少は選んでるような気がしますが、これも内容(書き方)に対する好き嫌いで別れる程度のことかなと思いますね
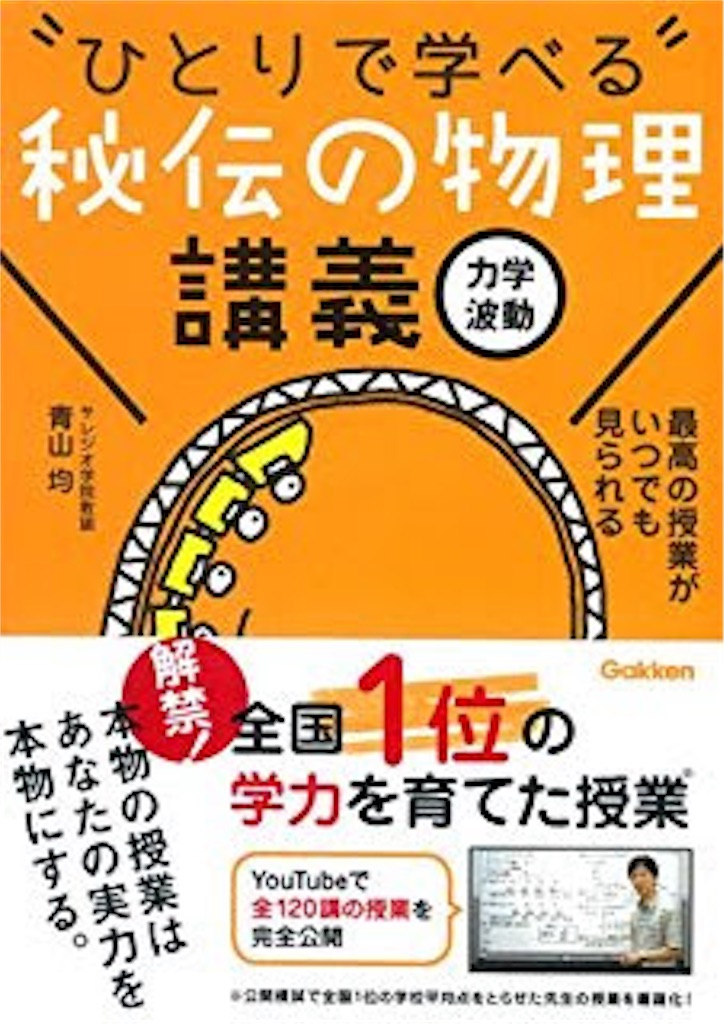

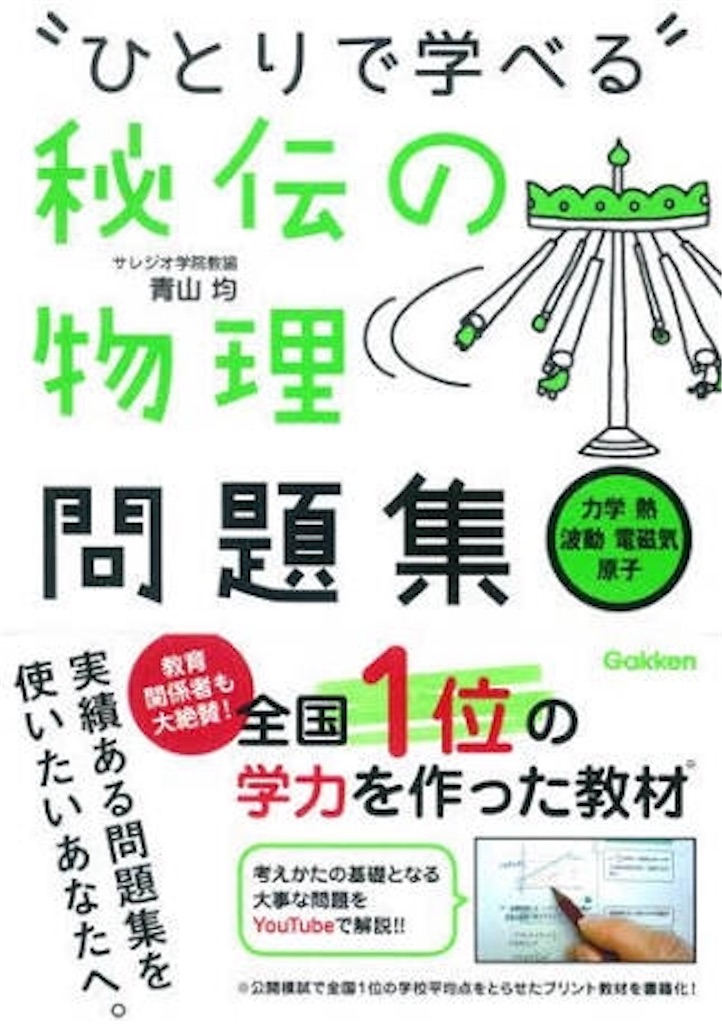
↓↓↓以下の①〜③今まで持ってて使いこなしてるなら買い替えずにそれでいいですが、コレを使ってて合わなかった人は他のものに変えてみてください↓↓↓
③『物理のエッセンス』『良問の風』
(エッセンス…オススメ度★★★☆☆
物理が苦手な人へのオススメ度★☆☆☆☆)
(『名問の森』は地方国公立医学部合格の目的には負担が多すぎて、あまり出ない事象が扱われてる点で、無駄かなと思いますので、あえてカットさせていただきました)
物理のエッセンスは
ある意味でエッセンス過ぎて
偏差値が60以上になってきて読むと解くコツなど得られるものが多いのですが、、、
基礎学力をつけるために使うと
(所々で省略されてることを自分で補って理解をしなくてはいけない部分があったリで)
良さが分からないまま繰り返したりしても力がついた実感を得にくい
(スグに点数が上がる感じがしない...と思えてしまうので、挫折の原因となる)
ということで、地方国公立医学部に合格するための教材としてはオススメしにくい状況があります
電磁気の説明は、さすがに電磁気に慣れてないと厳しいとは思います...
(→力がある程度ついてきて、自分にとって必要不必要が仕分けれる段階になると、考え方の抜けや穴が見つかりやすくなるので、その段階で読んだりするのはOKだと思います)
ただし
良問の風は
典型的な入試例題の選定がうまく
解説もそれほどクセがないため
使い勝手は悪くないですね
(ただ、物理の概念をエッセンスや授業などで理解し頭に入れてないと、やはり使いにくい面があります)
↑初めて使う人や、物理が苦手な人は、せめて秘伝の講義物を読み込んだ後、使ってみると良いとは思います
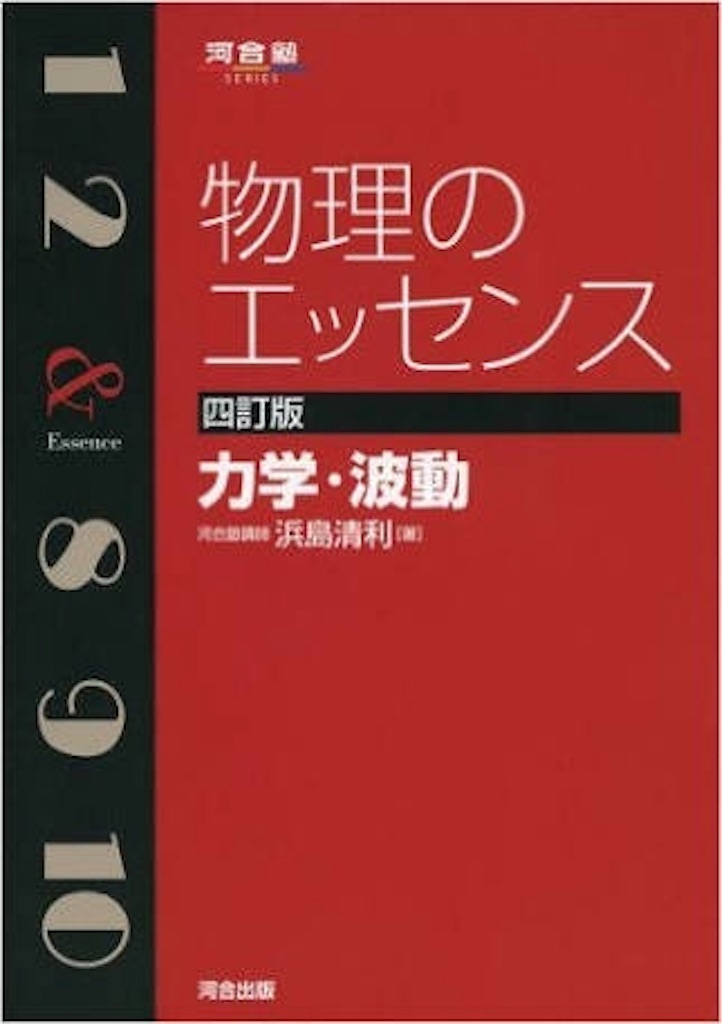


ここまでの①〜③の、問題選定レベル・難易度レベル・問題収録数は、ほとんど大差ないと考えておいてください
(入試頻出の典型的な問題で構成されています)
④為近先生の『解法の発想とルール(2冊)』本質をついた説明であるので、物理をじっくりやりたい人には向いている超良書だと思います
(ただし、「物理が好きで」じっくり時間をかけて勉強できる人向けです)

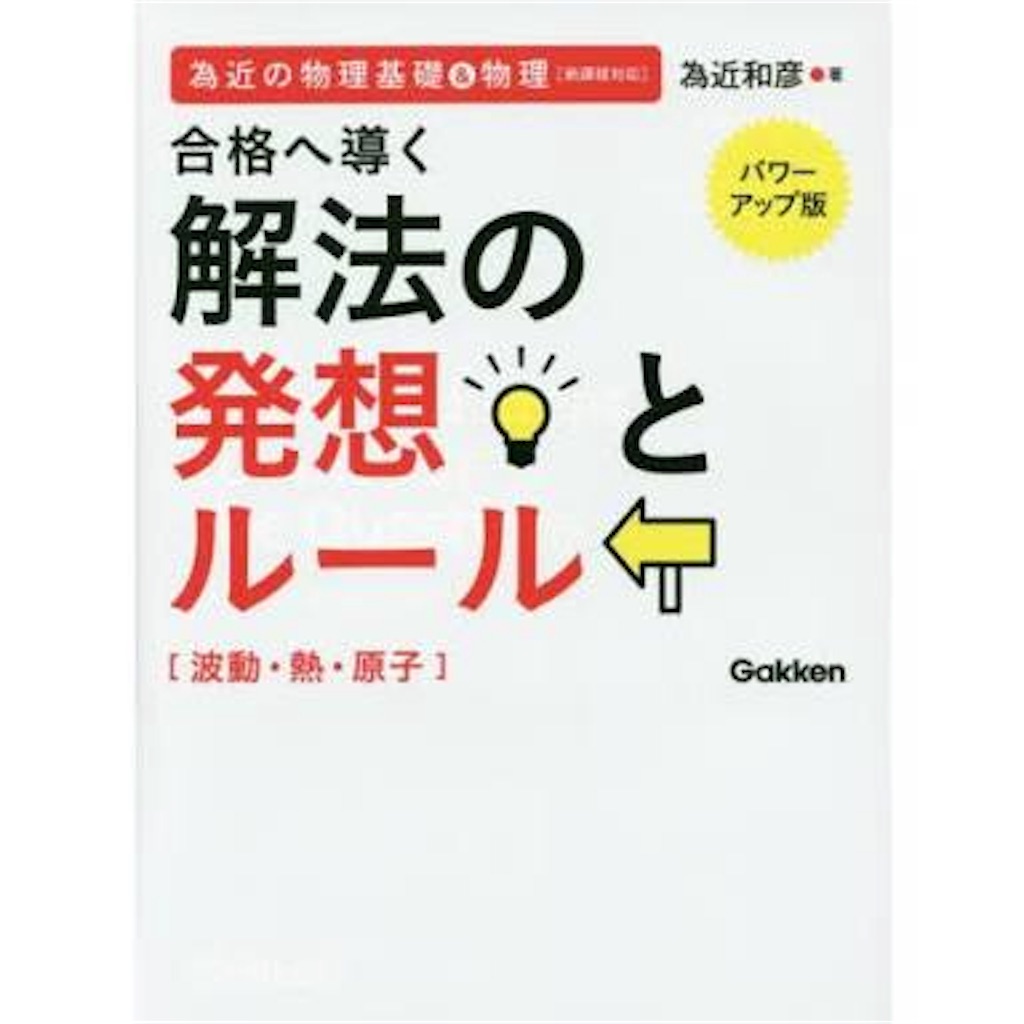
⑤漆原先生の『明快解法講座/最強の88題』は、解法パターン3ステップで先に紹介して、その手順で問題を解くという流れで解説されていますが、独特な解き方のため漆原先生の2冊をセットでやり込んで、漆原先生の解法へのアプローチを染み込ませてから、過去問スタートとなります
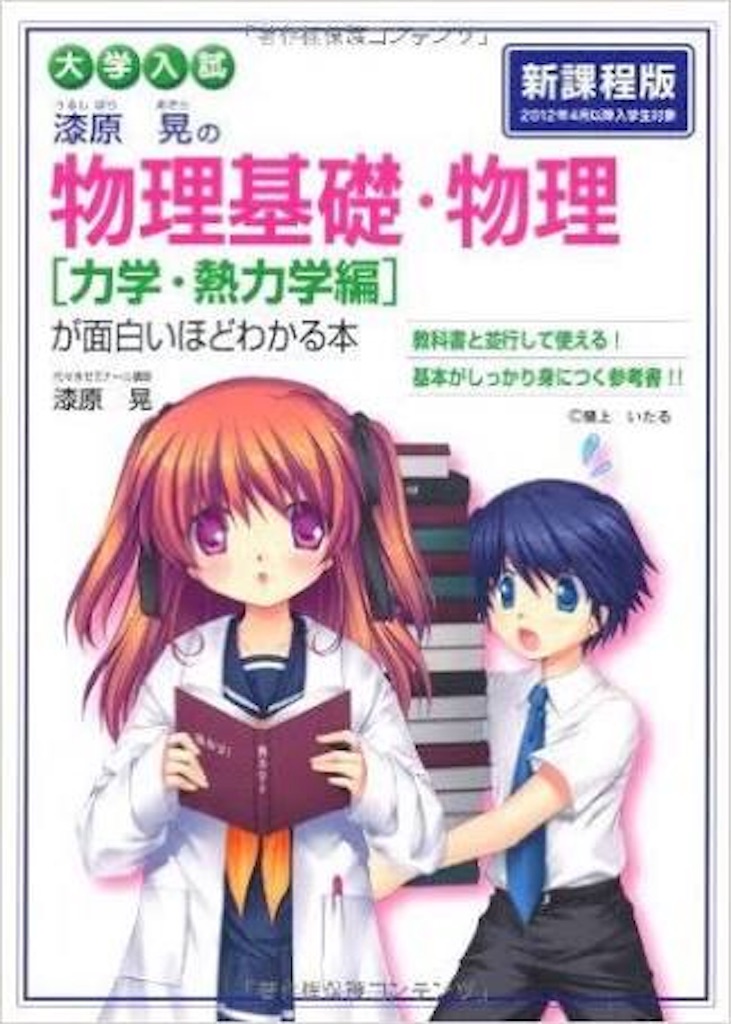


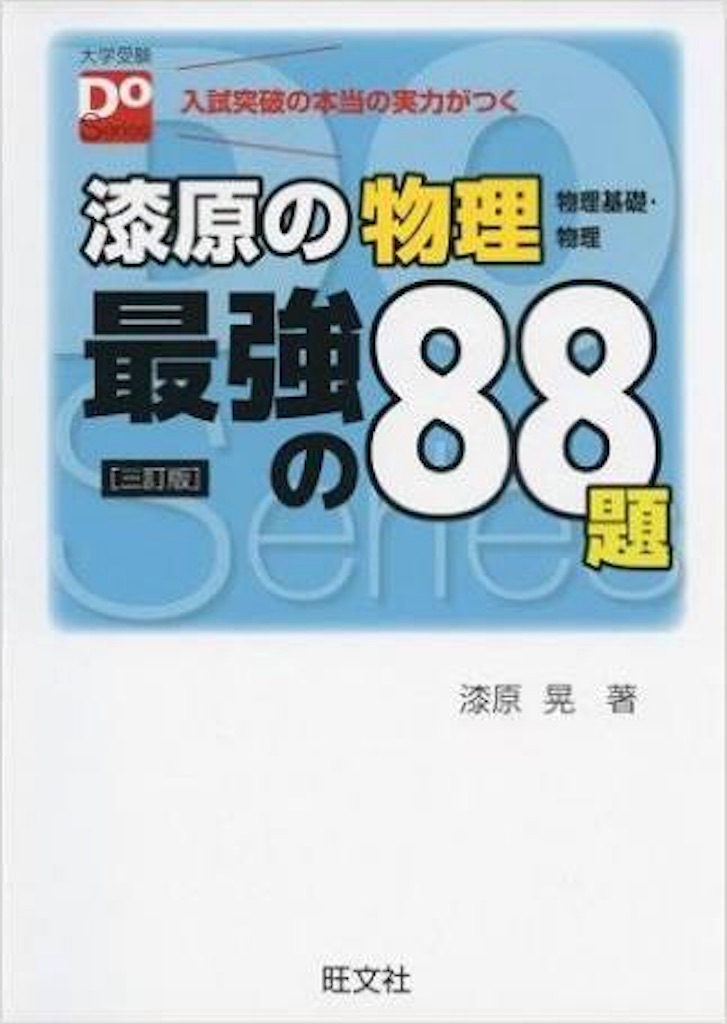
地方国公立医学部の二次試験で7〜8割という合格ラインを確保するには、設定の複雑さを考察する本来の物理的対応というよりは、『典型的な問題』に対して、正確にアタックする力を養成した方が得策です
(物理に良い意味でハマる人は、物理の面白さに魅せられ、暗記中心の化学や英語や、解法体系がしっかりしていない国語に時間をあまり割かない傾向がありますので、その辺りも考慮しての話です)
入試全体のバランスを崩してまで
物理をやり込む価値が
地方国公立医学部合格&その後の人生
にそれほど影響を与えないことを考えて
このような対策を提示しています
入試当日、物理が難しい時は
地方国公立医学部に合格する人でも
結局、あまり点数が取れず
他の教科次第となりますので
難しい問題を考え方込む本来の勉強の仕方
をあえて、『解法パターンへの対応』、という形に変えて勉強しておくのがリスクが少なくて良いとは思います
すでに高得点を取れる状況にある人は
そんなにハマらない程度に勉強をしていき、その分放置してる科目の底上げを行ってください
(↑国公立医学部は手を抜いた科目が1つ2つあるだけで、厳しい結果を突きつけられてしまいますので、学問への衝動を抑えて総合点を上げることへ特化していってくださいね)
得意科目の点数で大きな失点をカバーできるほど、地方国公立医学部も甘くありません
センターと二次試験のバランス
物理と化学のバランス
理数科目と英語と国社のバランス
そういう大局的な見方で
今の自分に必要な事をやり込む姿勢で
一日も早く医師になって
社会貢献していただけることを
切に望みます